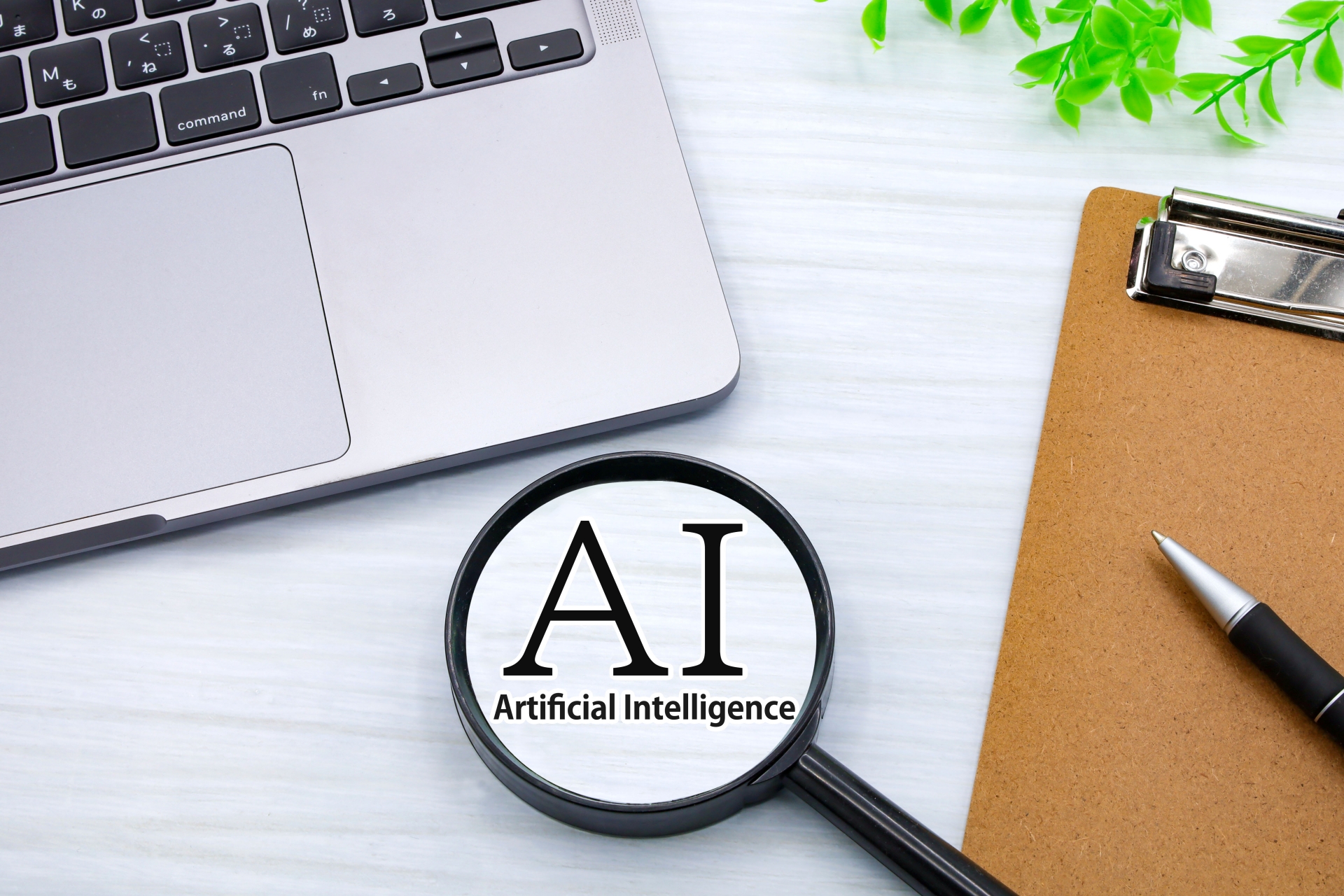「人生100年時代」という言葉が定着しつつあります。平均寿命が延びるだけでなく、健康寿命も徐々に長くなり、60代や70代でも現役で活躍する人が珍しくなくなってきました。では今から10年後、私たちの仕事環境はどのように変化しているのでしょうか。給料は上がるのか、定年後の人生はどうなるのか、年金制度は持続するのか。そして私たちはどのように働き方を選んでいけばよいのかを私見を交えて考えてみたいと思います。
まず注目すべきは労働力人口の減少です。少子化の影響で20~40代の人材はさらに希少となり、企業は中高年層を積極的に戦力として活用せざるを得ません。すでに「定年延長」や「定年廃止」を導入する企業が増えていますが、10年後には70歳まで働くことが一般的になっている可能性が高いでしょう。再雇用ではなく、シニア人材を本格的な戦力として位置づける流れは強まると思われます。
しかしその一方で、中高年を取り巻く職場環境は決して楽観できません。2025年度も既に早期・希望退職者公募は1万人を超えていて、企業が人材の若返りやコスト削減を進めている現実があります。表面的には「定年延長」と言いながらも、実際には中高年が働き続けられる環境が整っていない企業も少なくありません。10年後もこうした構造的な矛盾は残る可能性が高く、シニア世代は「会社に依存せずに働き続ける力」を身につける必要があるでしょう。
一方で、給料の水準は必ずしも右肩上がりになるとは限りません。AIやロボットの普及により、定型業務や事務作業は自動化が進んでいます。人間が担うのは「創造性」「人間関係」「判断力」が求められる領域であり、これを磨いた人は高く評価されるでしょう。つまり、スキルや専門性を磨く人材の給料は上がりますが、汎用的なスキルしか持たない人材の収入は横ばいか、むしろ減少する可能性があるのです。
年金制度については、現行の仕組みをそのまま維持するのは難しいと考えられます。支える世代が減少する一方で、受給者は増え続けるためです。10年後の年金は「生活の基盤を支える最低限の保障」に縮小していき、老後の生活を支えるのは「年金+仕事+資産運用」の三本柱となる可能性が高いでしょう。したがって、定年後も「完全に引退して余生を過ごす」というスタイルは現実的ではなく、「働きながら暮らす」ことが標準になっていくと思われます。
ここで重要になるのが「新しい働き方」です。すでにリモートワーク、副業解禁、フリーランスの拡大といった流れは始まっています。10年後にはこれがさらに進み、会社員でありながら複数の仕事を持つ「パラレルワーカー」や、自分の得意分野を小さく事業化する「小規模起業家」が当たり前になるでしょう。デジタル技術の発達により、オンラインで学び、仕事を獲得し、世界中の顧客とつながることが容易になるからです。
また、健康寿命の延伸は「70代でも現役で働く」という社会を現実のものとします。もちろんフルタイム労働ではなく、自分の体力やライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が主流となるでしょう。たとえば週3日のコンサルティング、副業的に地域の支援活動をする、趣味を活かして小規模ビジネスを展開するなど、働き方の選択肢は多様化していきます。
その延長線上に「起業」という選択肢も有効になります。従来の起業はリスクが高く、大きな資金や人材を必要とするものでした。しかし、デジタル基盤の整備とクラウドサービスの普及により、初期費用をほとんどかけずに事業を立ち上げられる環境が整いつつあります。自分の経験や強みを活かしたサービスを小さく始め、徐々に拡大していくスタイルは、中高年にとっても現実的な道です。特に、介護や教育、地域支援、健康・食といった「人と人をつなぐ分野」では、AIでは代替できない価値を提供できます。
結局のところ、10年後の仕事環境を生き抜くために必要なのは「柔軟性」と「学び続ける姿勢」です。会社や年金に依存するのではなく、自分のスキルや経験を武器に社会とつながり続けること。それが「人生100年時代」の最大のリスクヘッジであり、充実したセカンドライフにつながっていきます。
つまり10年後、働き方は一層多様化し、定年後も働くことが当たり前になります。そして「起業」は特別な人の選択肢ではなく、誰もが生活を支える一つの手段として検討できる時代になるでしょう。