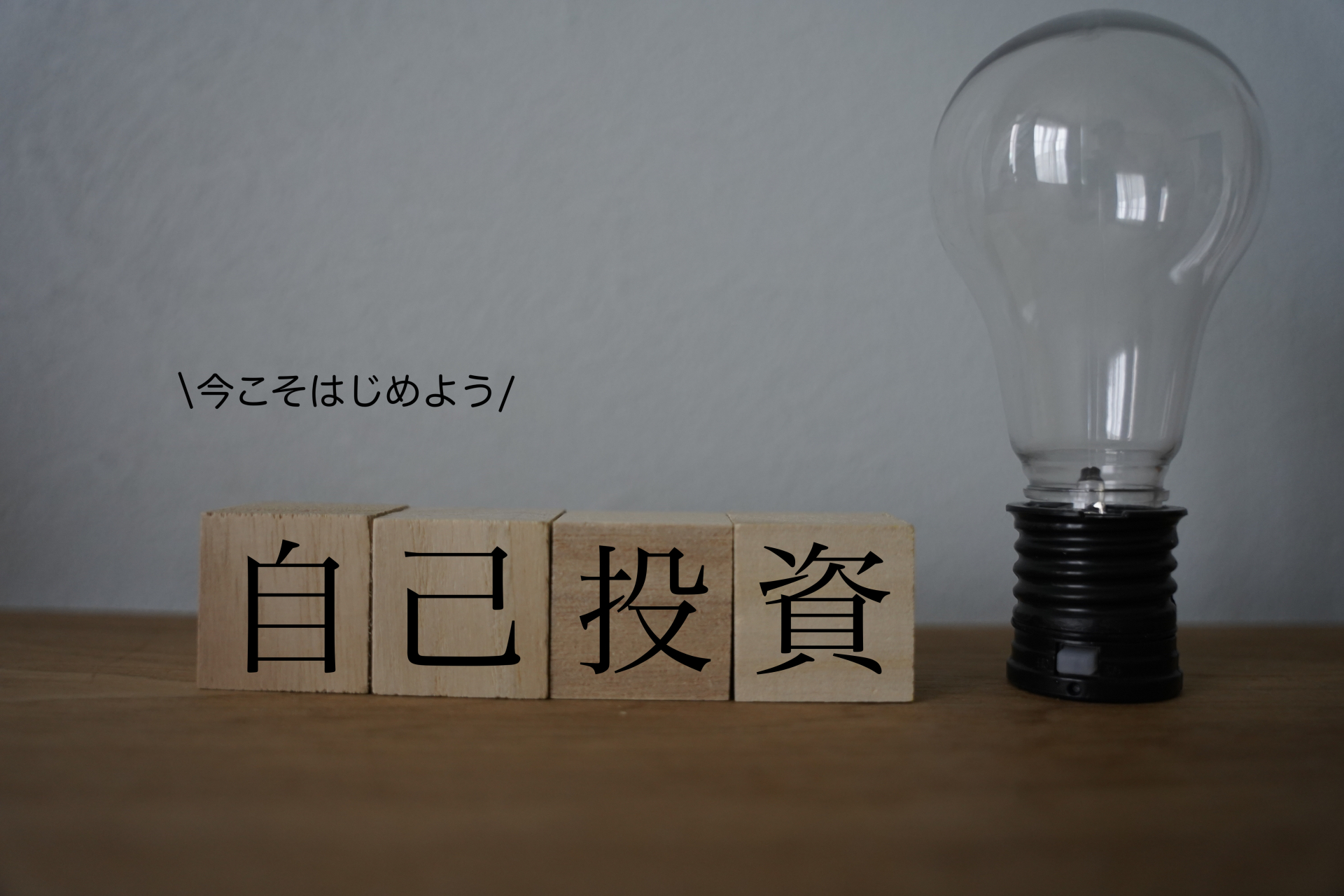2025年に入り、上場企業における「早期・希望退職」の募集人数が急増しています。1月から8月末までに募集が判明した対象人数は1万108人。前年同期比で約1.4倍に拡大し、すでに2024年通年の募集人数を上回りました。募集企業数自体は前年より減ったものの、一社あたりの募集規模が大型化しているのが特徴です。
注目すべきは、募集企業の約6割が黒字であるという点です。かつては赤字転落企業によるリストラが主流でしたが、近年は「将来に備える構造改革」「中長期の競争力強化」を目的に、経営状態が堅調な企業であっても人員削減に踏み切っています。
具体例として、日産自動車は2027年度末までに追浜工場での車両生産を終了し、九州工場へ統合する計画を発表しました。世界全体で2万人規模の削減を公表しており、国内でも相当数の人員整理が進むと見られます。パナソニックHDは国内外で1万人(国内5,000人)の削減を進行中。ジャパンディスプレイも「BEYOND DISPLAY」戦略のもと、茂原工場閉鎖などで1,500人を削減し、9月には1,483人が応募したことを発表しました。
また、日清紡HDでは無線・通信事業の再編に伴い400人、NIPPON EXPRESSホールディングスでは300人といった規模の募集も行われています。これらはいずれも黒字企業であり、外部環境の変化を先取りした「攻めのリストラ」といえます。特に製造業では、トランプ関税をはじめとした国際的な貿易摩擦が再燃するリスクを見越し、早めの人員スリム化に踏み切る動きが加速しています。
出展:東京商工リサーチ
上場企業の「早期・希望退職」募集 1-8月で1万人超え 募集の大型化で前年同期比1.4倍増、前年1年間を上回る | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ
では、こうした潮流の中で、私たちビジネスマンはどのように備えるべきでしょうか。Taigaコンシェルジュとしての視点から、いくつかのポイントを整理しておきたいと思います。
1. 「自分の市場価値」を客観的に見直す
黒字企業でも人員削減に踏み切る時代です。会社の業績に頼って「安泰」と考えるのはリスクが高いと言えます。まずは自分のスキルがどの分野で通用するのかを確認し、市場での需要を見極めることが必要です。専門職や資格の有無に限らず、「この人にしかできない」強みを言語化しておくことが、転職や独立時の大きな武器になります。
2. 複線キャリアを意識する
これからは「一社一筋」よりも、「会社+α」のキャリア形成が現実的です。副業やパラレルキャリアを通じて収入源を複数持つことは、単なるリスク分散ではなく、新しい挑戦のきっかけにもなります。特に50代以降の方は、定年後を見据えたスモールビジネスや資格活用を早めに準備しておくと安心です。
3. ネットワークを広げる
企業が人員削減に動くとき、真っ先に問われるのは「この人を残す必然性があるか」です。その判断はスキルだけでなく、人脈や信頼関係にも左右されます。社内外を問わずネットワークを広げ、情報交換を欠かさないことが、いざという時の転機を支えます。
4. 資産と生活設計を再点検する
早期退職は、退職金や割増金が支給される一方、その後の生活基盤をどう組み立てるかが課題です。住宅ローン、教育費、老後資金といったライフプランを再点検し、「もし来月、希望退職の打診があったらどうするか」という想定をシミュレーションしておくことが肝心です。
5. 「学び直し」をためらわない
AIやデジタル化の進展により、従来のスキルが通用しなくなるケースも増えています。オンライン講座や資格取得を活用し、学び直しを続けることが、50代以降でも新しい仕事に挑戦できる力を養います。
まとめとして
2025年の「早期・希望退職1万人超え」は、一部の企業だけの問題ではなく、すべてのビジネスマンに突きつけられた現実です。黒字でも削減が進む今、「自分の働き方をどう再設計するか」を常に意識しておく必要があります。
つまり大切なのは、「会社に残れるか」よりも「会社を離れても生きていけるか」という視点です。キャリア、資産、学び、人脈。これらを少しずつ準備することで、不測の事態が訪れても前向きな選択肢を持てるようになります。「いつか」ではなく「今から」。人生100年時代を安心して歩むために、自分自身の備えを始めていきたいものです。