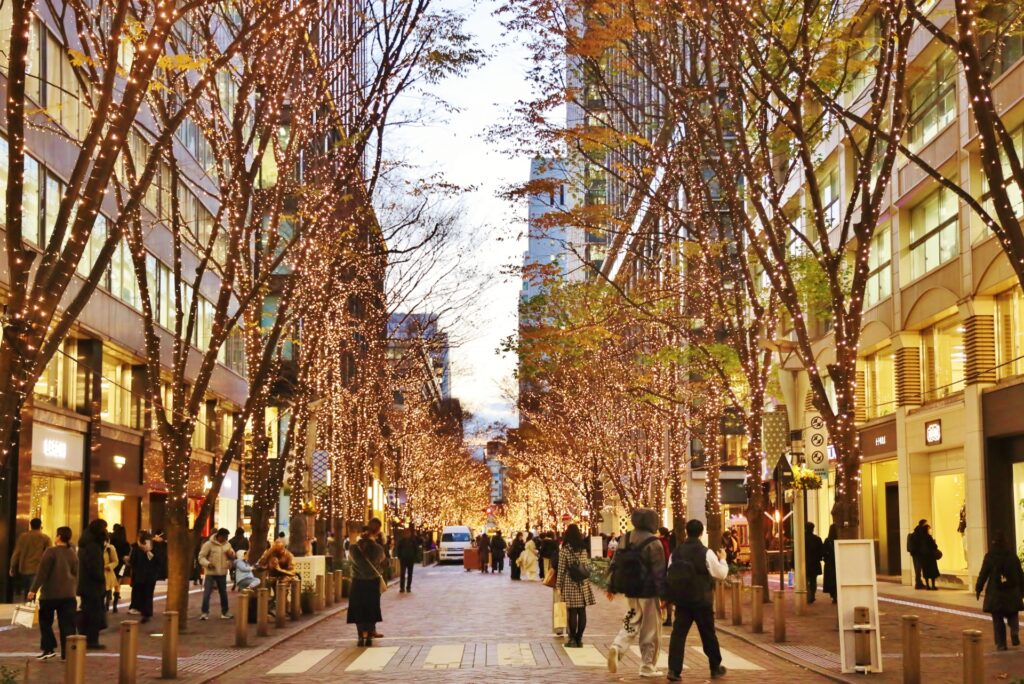-

起業家は「つり革」を掴まない⁈ ― 毎日の通勤電車から見える“未来の握り方”
朝の満員電車。人の流れ、時間、速度——すべてが決められたリズムの中で進んでいきます。手元には当たり前のようにある「つり革」。丸型、三角型、縦配置や横配置など、実は多様なのに、その違いに気づくことは少ないでしょう。鉄道会社の歴史や考え方が反... -

日本企業ではかつて議論された#「40歳定年」構想が、いま現実的な制度として静かに浸透しつつあります。企業が黒字であっても早期退職を募ることはもはや珍しいことではなく、中高年層のキャリア形成をめぐる環境は、大きな転換点を迎えています。
その象徴的な事例が、マツダが今年度導入した希望退職制度です。マツダは12月1日、今年度に設けた希望退職制度の応募者が、当初想定していた上限500人に達し、予定よりも早く募集を締め切った。本来、2025〜26年にかけて最大4回の募集を行う計画を立ててい... -

40代・50代こそが、セカンドライフの土台づくりのゴールデンタイム 定年延長は“猶予期間”。70歳以降を生き抜く力は、いま育てる。
近年、「70歳代で自己破産する人が増えている」というニュースが注目されています。高齢者の破産件数は2010年代以降じわじわと増加し、自己破産者の中で60〜70代が占める割合は年々高まっています。背景には、年金だけでは生活が成り立たない現実、医療費... -

50代の“早期退職ショック”──年収半減でも転職が決まらない現実と、日本型キャリアの問い直し
「これまで会社のために走り続けてきた。なのに、いざ外に出てみると“価値”を説明できない」。最近、50代の方からこうした声を聞く機会が増えています。 日産自動車、パナソニックHD、三菱電機など、日本を代表する製造業が相次いで早期退職の募集に踏み切... -

「女性の美と食べることに関するビジネスは不況知らず」──この言葉は、日本マクドナルド創業者・藤田田氏がたびたび語った「女性・子ども・老人を相手にする商売に不況はない」という考え方を端的に表したものです。
2025年11月10日、資生堂が赤字決算を発表したというニュースは、多くの人にとって「時代が変わった」ことを実感させる出来事だったと思います。「不況知らず」神話の崩壊──人生100年時代の働き方設計化粧品業界は長らく安定業種の代表とされてきました。景... -

小規模起業—「うまく行かない日」が未来を作る
10月になると思い出すことがあります。それは、私が自然栽培無農薬茶販売の新規事業を始めた時期です。当時、ベトナム駐在の経験を活かし、現地の「蓮芯茶」と日本の無農薬自然栽培茶をブレンドしたオリジナル商品を思いつき商品化しようと考えました。健... -

フリーランスから起業という選択肢 ― 副業から始める人生100年時代の働き方
近年、「会社に頼らず、自分の力で働く」という考え方が広がりつつあります。年金世代だけでなく、会社員や子育て世代、学生までもがフリーランスや副業を通じて自分の仕事をつくり出しています。フリーランスは「若い人の働き方」と思われがちですが、実... -

#黒字でも人員削減 ― 希望退職が示す“静かな構造変化”
三菱電機が発表した「53歳以上の希望退職募集」は、業界に大きな衝撃を与えました。なぜなら、同社は2025年3月期に売上・営業利益ともに過去最高を更新する見通しであり、「経営不振によるリストラ」とは言えないからです。しかし、これは決して三菱電機だ... -

不動産×起業 ― 資産を動かす次の一手
少子高齢化が進む日本では、空き家や使われなくなった店舗が全国で増え続けています。総務省の調査によると、全国の空き家はおよそ900万戸にのぼり、実に7戸に1戸が空き家という時代です。これらの不動産を「負動産」として処分に困るのではなく、「活きた... -

#宅建士資格取得で描く人生100年時代のデザイン―2025年の宅建資格試験まで一ヶ月を切り目下追い込み中!
人生100年時代といわれる今、私たちの生き方は「働く期間」と「余生」の境界が曖昧になりつつあります。60歳で一区切りをつけるのではなく、その後の20年、30年をどう生きるかが、一人ひとりに問われています。私は「テナント事業」「セカンドライフの相談...