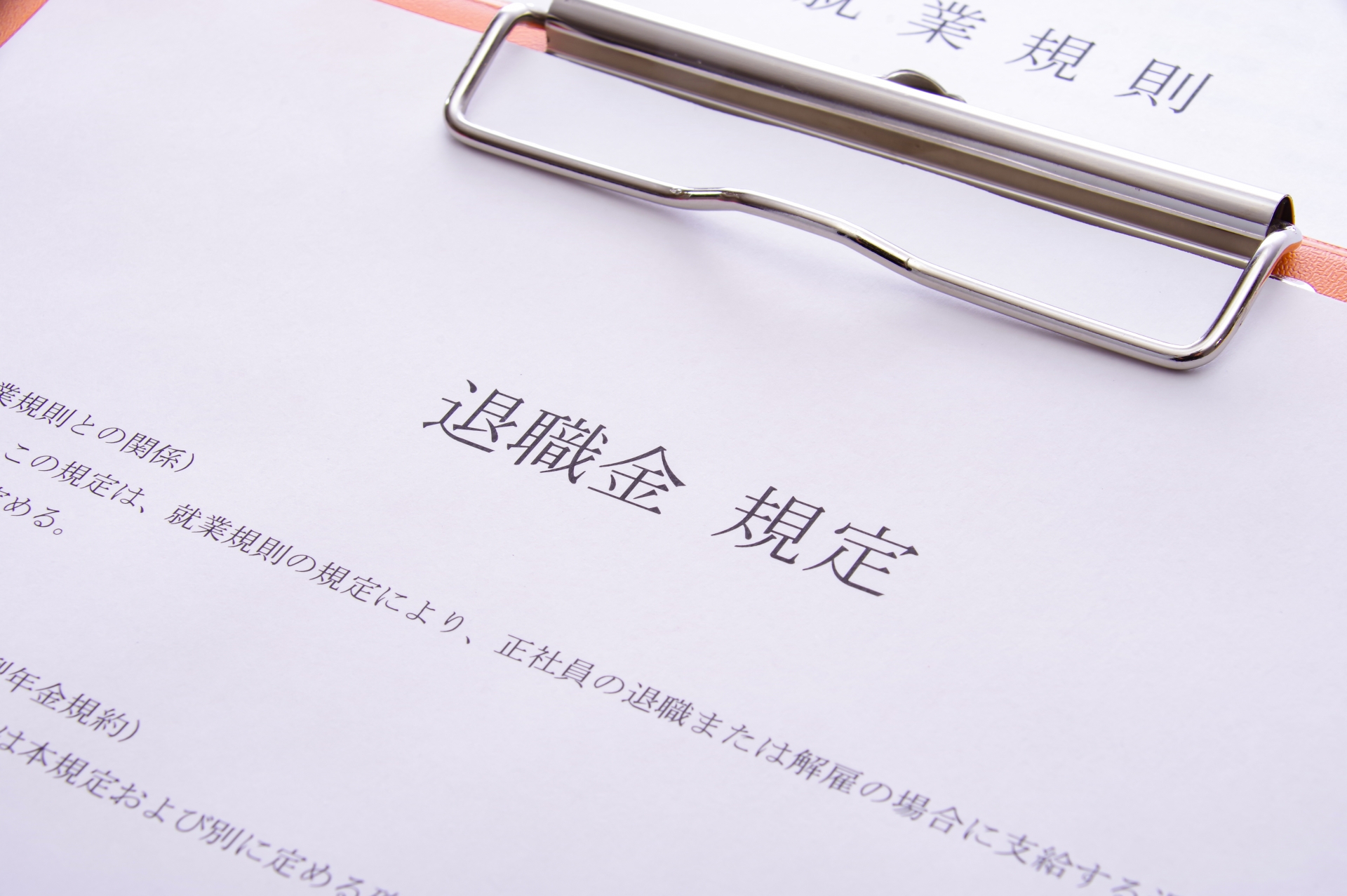かつて日本人の老後資金の大きな柱とされてきた退職金制度。しかし近年、その存在は揺らぎ、「定年まで勤め上げれば退職金で安心」という時代は過去のものとなりつつあります。いま求められるのは、自らの手で将来に備える主体的な姿勢です。ここでは、退職金制度の最新事情と、それを踏まえた資産形成のあり方を整理してみたいと思います。
退職金制度を持たない企業は約4社に1社
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によると、退職金制度を設けていない企業は24.8%。実に4社に1社が「退職金なし」という状況です。企業規模別に見ると、大企業(従業員1000人以上)では90.1%が制度を導入しているのに対し、中小規模(30~99人)では29.5%が制度を持たず、約3割に達します。業種差も大きく、「宿泊業・飲食サービス業」では半数以上が制度を導入していません。退職金制度は法的義務ではなく、各社の経営判断に委ねられているため、このような格差が生まれています。
制度廃止や未導入が増える背景
退職金制度を廃止、あるいは導入しない企業が増える理由は大きく二つあります。第一に、企業にとっての財務的負担です。退職金は長期勤続を前提とし、将来の支払原資を会社が準備し続ける必要がありますが、経済環境の不透明さは企業にとって大きなリスクです。第二に、人材流動化の進展です。転職が一般化し、一社に定年まで勤める人が減ったことで、従来の「長期勤続を報いる制度」としての退職金は時代にそぐわなくなりました。その結果、退職金を廃止して給与や賞与に上乗せする企業や、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」へ切り替える企業が増えています。
退職金がない場合に必要な老後資金対策
退職金がない場合、あるいは少ない場合、自ら老後資金を積極的に準備することが不可欠です。まずは「老後に必要な生活費」を把握し、退職からの生活期間を見積もって逆算することが重要です。総務省の家計調査では、高齢夫婦世帯は年間収支が赤字となるケースが多いことが示されています。
具体的な対策としては、
・預金や積立型保険による安定的な蓄え
・投資信託や株式などによる資産運用
・iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用(掛金が全額所得控除となる税制優遇)
が一般的ですが、預貯金は低金利で増えにくく、投資にはリスクも伴います。
また、会社員の場合、制度が途中で見直され突然廃止されることもあるため、自分の勤める会社の制度を定期的に確認することも大切です。
私は投資で失敗した経験から、小規模起業へと舵を切りました。再雇用の道も、年齢を重ねるにつれて選択肢が狭まっていくと考え、再雇用と起業を組み合わせたハイブリッド就労で試行錯誤を重ねる中、なんとか「生涯現役」の見通しを立てることができたのは幸運でした。
「時間をお金に変える仕事」への投資――すなわちリスクを抑えながら生涯続けられる小規模起業は、セカンドライフの有効な選択肢の一つだと考えています。年金だけでは不足する生活資金を補えるだけでなく、生きがいにもつながるからです。
退職金制度のある企業の退職金はこの30年で・・・・
退職金の支給額はこの30年で大きく減少しています。厚生労働省「退職給付(一時金・年金)の実態調査」によれば、
・1990年代初頭:大卒・管理職で平均約3000万円
・2000年代:2500万円前後
・2023年:1896万円
と推移しており、とくに中小企業では金額がさらに低い傾向にあります。成果主義の普及や勤続年数の短縮化も背景にあり、「誰でも高額退職金を得られる時代」はすでに終わったといえます。また制度面でも、「退職一時金」から「確定拠出年金(DC)」や「確定給付年金(DB)」へ移行が進み、運用成果次第で受取額が変動するようになりました。いまや従業員の金融リテラシーが将来を左右する時代です。
セカンドライフに備えるために
こうした状況を踏まえ、私たちが考えるべき備えは次の三点です。
- 退職金を老後資金の中心と考えない
退職金はあくまで一時的な資金の一部にすぎません。公的年金や個人の貯蓄・投資、不動産収入などと組み合わせて総合的な資産設計を行うことが必要です。 - 税制優遇制度を活用する
iDeCoやNISAといった制度を用い、現役時代から計画的に積み立て・運用することが将来の安心につながります。 - 「働き続ける力」を持つ
資格取得やスキルアップ、副業や小規模起業などを通じて、セカンドライフでも収入を得られる仕組みを作っておくことは、生活の安定だけでなく生きがいにも直結します。
まとめとして
退職金制度はもはや「自動的に老後の安心をもたらす仕組み」ではなくなりました。支給額の減少や制度変更リスクを前提に、自らが主体的に備える姿勢が欠かせません。セカンドライフは与えられるものではなく、自らデザインするもの。退職金の減少を嘆くよりも、むしろ転機と捉え、自分らしい第二の人生を築く準備をいまから始めることが大切です。
参照: 厚生労働省 令和5年就労条件総合調査の概況