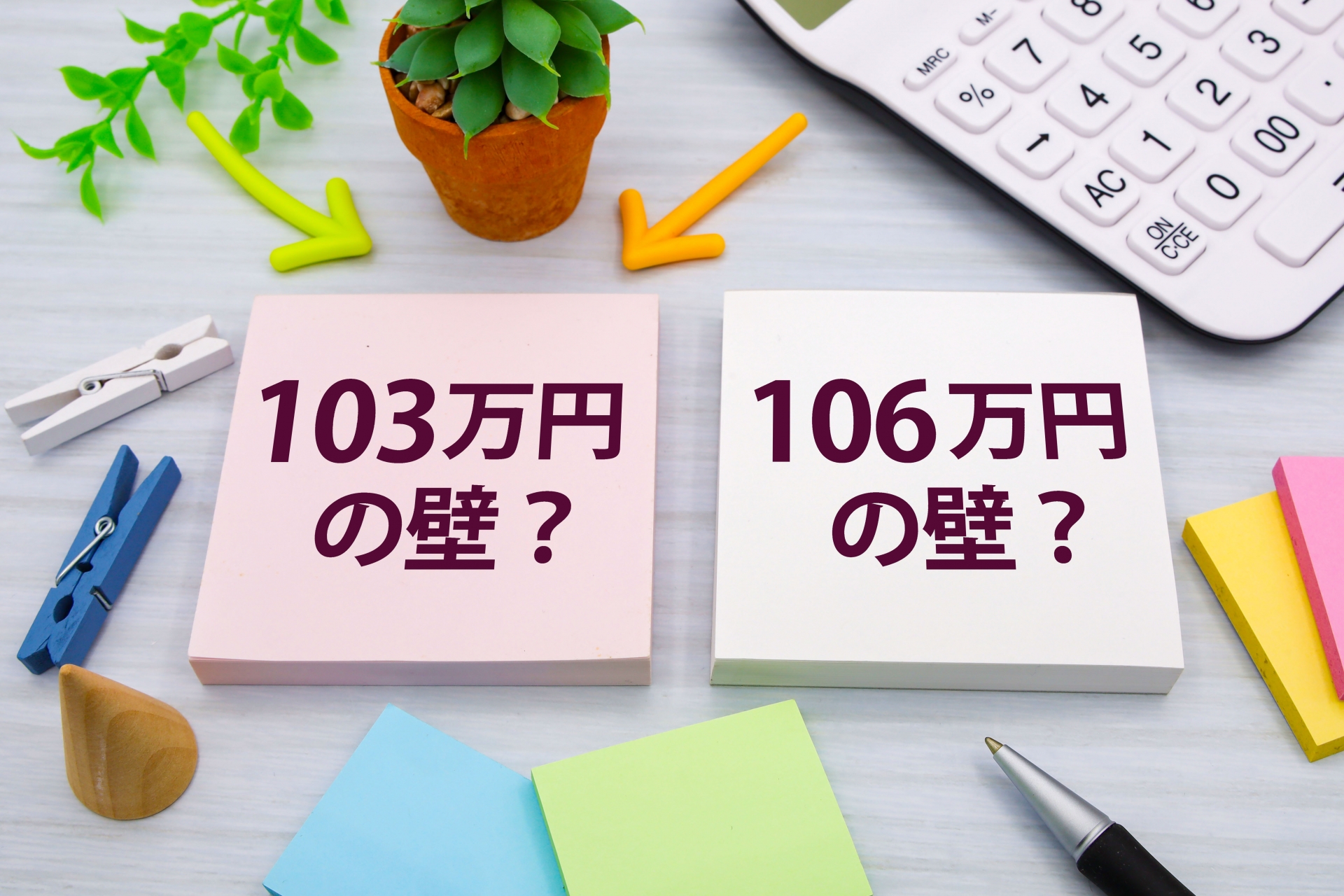2025年5月16日に政府が閣議決定し国会に提出した年金制度改革法案では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃が盛り込まれました。これは、パートタイムなど短時間労働者が一定の年収を超えると厚生年金の保険料負担が発生し、手取り収入が減少することから、労働時間を抑える「働き控え」が生じる問題に対応するための措置です。
パートやアルバイトなど、短時間労働をしている人々にとって、大きな障壁となっていた「年収の壁」。中でもよく知られているのが「103万円の壁」と「106万円の壁」です。現在、政府ではこの2つの年収制限について、2025年からの撤廃を含めた制度改正を検討しています。
103万円の壁とは?
「103万円の壁」とは、給与所得者が年収103万円を超えると所得税が課税される制度です。多くのパートタイマーや学生アルバイトが、この壁を超えると手取りが減ってしまうことを懸念して、勤務時間を調整する傾向が見られました。具体的には、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計である103万円を超えると、課税対象となり、実質的な手取りが減る可能性があるというものです。
この制度が、労働意欲の低下や就労抑制につながっているとの指摘もあり、政府は103万円の壁の撤廃を検討しています。
103万円の壁が撤廃されるとどうなる?
2025年から、年収103万円の壁が撤廃され、新たに123万円まで所得税が非課税となる仕組みが導入される見込みです。これは、基礎控除が58万円、給与所得控除が65万円に引き上げられることで実現します。つまり、年収123万円までであれば、引き続き所得税は課されないため、働き方の自由度が広がります。
この改正により、これまで103万円を意識して労働時間を制限していたパートや学生アルバイトも、より柔軟に働くことが可能になります。年収が増加しても、税負担を気にする必要がなくなるため、労働意欲の向上にもつながると期待されています。
さらに、学生アルバイトに適用されていた特定扶養控除の適用上限についても見直しが検討されています。これまでは年収103万円を超えると親の税負担が増すため、アルバイトの収入に制限を設けざるを得ませんでしたが、今後はこの上限が150万円に引き上げられる可能性があります。これにより、親の扶養控除の適用範囲が広がり、学生側・親側の双方にとって経済的メリットが生まれることになります。
106万円の壁の見直しも進む
一方、「106万円の壁」は社会保険加入義務が発生する基準であり、月収にして約8万8,000円以上、年収で約106万円以上になると、一定条件を満たす場合に厚生年金や健康保険への加入が義務づけられます。
これにより、手取りが減るのを嫌がって働き方を調整するケースが多く見られました。特に、配偶者の扶養に入りながら働く人にとっては、この壁を越えることで保険料負担が発生し、収入が増えても手取りが逆に減るという逆転現象が課題となっていました。
2025年からの制度改正では、この106万円の壁についても見直しが行われ、労働時間や収入を自由に選びやすい環境の整備が進むと見込まれています。これにより、特に女性や高齢者など、柔軟な働き方を望む層の就労が後押しされるでしょう。
年収の壁の種類
年収の壁には、税制上での年収の壁と社会保険に関係するもの大きく分けて6つ
| 年収の壁 | 発生する負担 | 影響 |
| 100万円の壁 | 住民税 | この年収を超えると、住民税が発生し、収入からの負担が増える |
| 103万円の壁 | 所得税 | この年収を超えると、税制上の扶養から外れ所得税がかかるため、受け取る手取り額が減少する |
| 106万円の壁 | 社会保険料 ※勤務先が従業員51人以上など条件を満たすとき | 勤務先が51人以上の企業で働く場合、この金額を超えると社会保険料がかかり、手取り額が減少する |
| 130万円の壁 | 社会保険料 | この年収を超えると、扶養から外れるため、社会保険料の負担が増加する |
| 150万円の壁 | 配偶者特別控除額が減る | この年収を超えると、配偶者特別控除が減少し手取り額が減少 |
| 201万円の壁 | 配偶者特別控除がなくなる | この年収を超えると配偶者特別控除が全く適用されなくなり配偶者が働く場合の収入計画に影響 |
参照:「年収の壁」撤廃はいつから?103万円・106万円それぞれの時期を解説 – ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに
住民税への影響は?
今回の改正は主に所得税に関する見直しであり、住民税についてはそれほど大きな変化はありません。給与所得控除の引き上げは住民税にも反映されますが、その額は10万円程度にとどまるとされており、住民税の負担増は相対的に小さいと考えられています。そのため、年収が123万円に達しても、所得税・住民税を合わせた実質的な負担は軽く、多くの人が「働き損」と感じることなく収入を得られるようになるでしょう。
企業側や人事労務にも影響
このような年収の壁の見直しは、労働者だけでなく企業にも影響を及ぼします。特に年末調整を担当する人事労務担当者は、新しい制度に対応するための情報収集や実務対応が求められます。従業員の働き方に関する相談が増える可能性もあるため、早めの準備と制度理解が重要です。
審議は継続中で、流動的な部分や変更点など出てくると思います。各個人の属性によっても制度の適用は変わってきますので、専門家への相談、また各自での情報のアップデイトをお願いします。