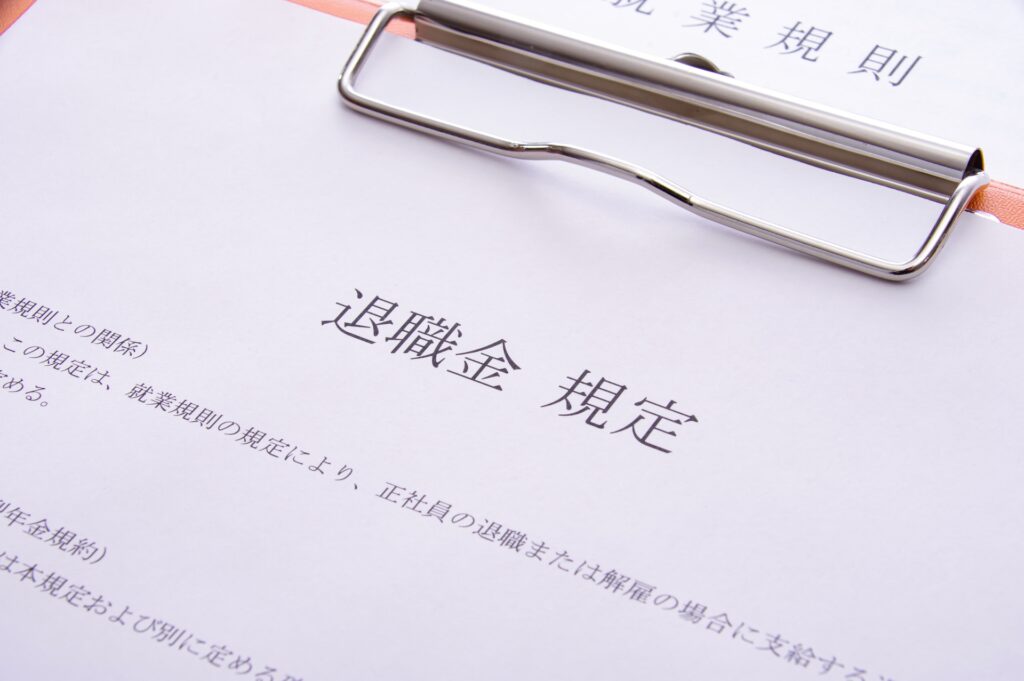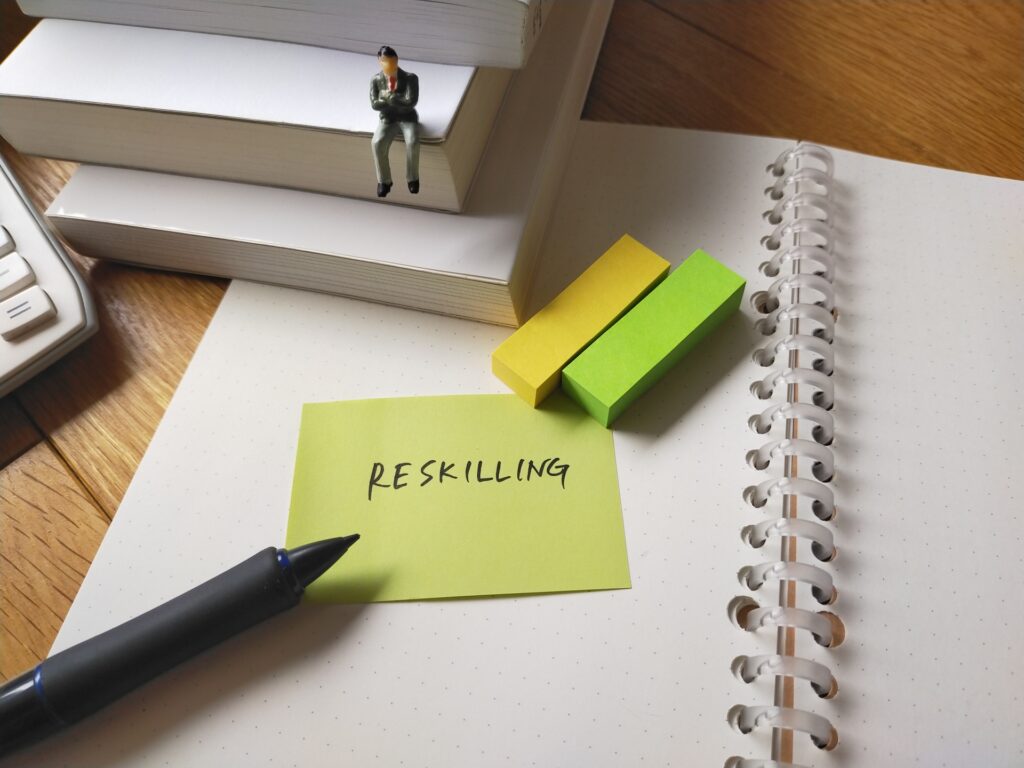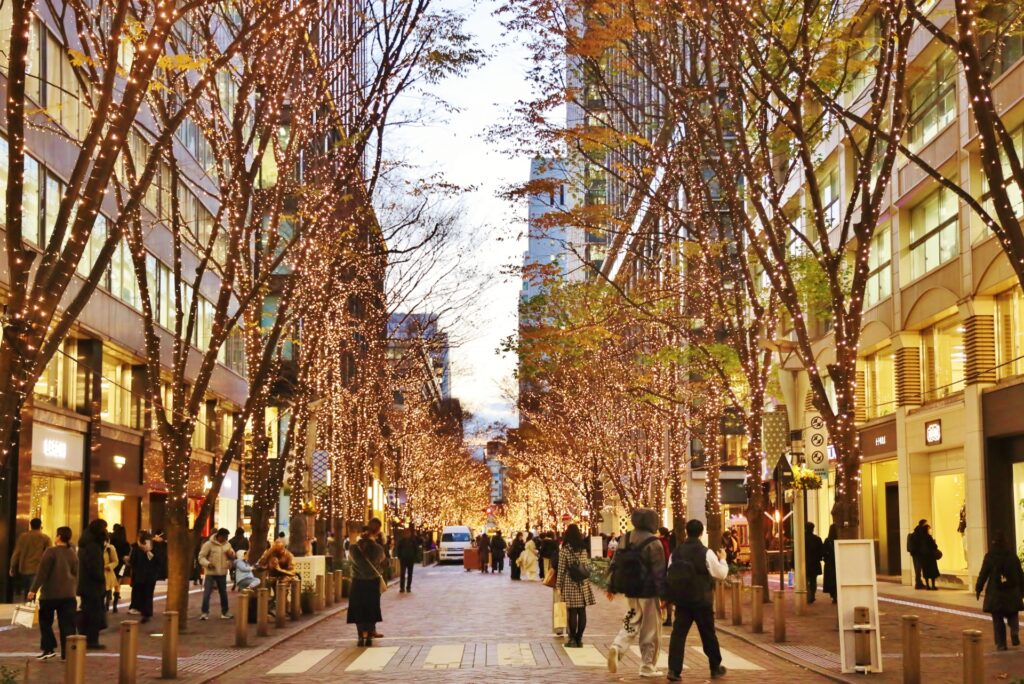-

#人生100年時代、これから10年後の仕事と働き方を見据えて
「人生100年時代」という言葉が定着しつつあります。平均寿命が延びるだけでなく、健康寿命も徐々に長くなり、60代や70代でも現役で活躍する人が珍しくなくなってきました。では今から10年後、私たちの仕事環境はどのように変化しているのでしょうか。給料... -

#早期・希望退職「1万人超時代」― ビジネスマンが今から備えるべきこと
2025年に入り、上場企業における「早期・希望退職」の募集人数が急増しています。1月から8月末までに募集が判明した対象人数は1万108人。前年同期比で約1.4倍に拡大し、すでに2024年通年の募集人数を上回りました。募集企業数自体は前年より減ったものの、... -

#定年延長と再雇用の行方 ― 安定か、さらなる試練か
日本では少子高齢化の進展により、労働力不足が深刻化しています。政府は高齢者の就業促進を重要課題と位置づけ、定年延長や再雇用制度の普及を後押ししてきました。2021年には「70歳就業機会確保法」が施行され、企業には70歳まで働ける仕組みづくりが努... -

#セカンドライフにおける仕事と小規模起業の可能性
50代に入ると、多くの人が自分の仕事との向き合い方に変化を感じるようになります。30代、40代までは家庭を支える責任、子どもの教育費、住宅ローンの返済、会社での昇進や評価など、目の前の課題に追われながら「生活のための仕事」を続けてきた方が大半... -

#定年後 9割が選択する再雇用の過酷な現実
定年延長や再雇用制度は「長寿社会における安定的な雇用確保」として注目を集めてきました。日本では多くの企業が60歳定年を採用していますが、実際にはそのまま引退する人は少数派です。厚生労働省の調査によると、60歳で定年を迎えた後、実に9割近くの... -

#退職金制度が無い会社は何割くらいあると思いますか? 退職金制度の現状とセカンドライフへの備え
かつて日本人の老後資金の大きな柱とされてきた退職金制度。しかし近年、その存在は揺らぎ、「定年まで勤め上げれば退職金で安心」という時代は過去のものとなりつつあります。いま求められるのは、自らの手で将来に備える主体的な姿勢です。ここでは、退... -

#定年後、家の中に“もう一人の自分”が常駐!? 熟年離婚を防ぐための4つの心がけ。「夫が家にずっといる」が苦にならない夫婦の習慣とは?
定年は夫婦関係にも大きな転機になる長年働いてきた夫が定年を迎え、家にいる時間が増えると、多くの妻たちが心のどこかで感じることがあります。それは「夫がずっと家にいるのが、なんだかつらい」という本音です。決して夫を嫌っているわけではなく、む... -

#資格は“肩書き”ではなく、“武器”になる。~50代からの一歩が、セカンドライフの可能性を広げる鍵に~
「定年後、何をして暮らしていこうか」と考えたことはありませんか?人生100年時代を迎え、50代に差しかかったとき、ふと「この先、どう生きていけばいいのだろう」と考える方も多いのではないでしょうか。企業による再雇用制度が整いつつあるとはいえ、多... -

#コアターゲット外だからこそ、シニア市場は面白い。大企業が手を出しにくい“最後の成長市場”——シニアの力で切り拓く未来
企業やテレビ局がマーケティング活動において重視する「コア視聴率」とは、13歳から49歳までの男女による個人視聴率を指します。これはマーケティングの世界では常識ともいえる基準であり、この年齢層を超えると広告の反応率が極端に下がるとされています... -

# 「2000万円問題」に潜む見落とし――老後に増す社会保障費の負担
「老後資金2000万円問題」が話題になってからしばらく経ちました。この問題の根拠となった試算は、平均的な年金受給額と平均的な高齢者の生活費の差額、約5万円の赤字を月々積み重ねると、退職後30年間で約2000万円の不足が生じる、というものでした。しか...